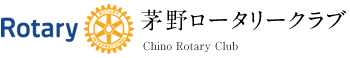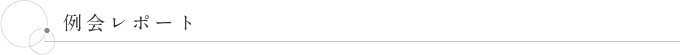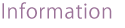4月19日(火)は諏訪大社ロータリークラブ、富士見ロータリークラブ、茅野ロータリークラブの3クラブ合同例会である「桜の花に乾杯」が開催されます。ご参加の程宜しくお願いします。
今日は少しお酒の話をさせて頂きます。酒造りの歴史は古く、奈良時代には造酒司(ミキノツカサ)という役所が作られ、朝廷のための醸造体制が整えられていました。平安時代には、米、麹、水で酒を仕込むようになり、さらに燗(カン)でも飲まれていたようです。
鎌倉、室町時代には、寺院、神社が酒を造るようになり、京都辺りで造り酒屋が出始めます。江戸時代になると、寒い時期に仕込む寒造りや保存性を高めるための火入れ(低温殺菌法)、香味(コウミ)を調えるために柱焼酎(ハシラジョウチュウ)を混ぜるなどの、現在に連なる酒造りの原型が見られます。
明治時代に入ると、国立の醸造試験所が開設され、酒は醸造、流通、販売が許認可制になり、昭和に入ると、縦型精米機が開発され、微生物や温度管理が容易なホウロウタンクが登場します。家付き酵母を採取し、分離、純粋培養する方法が開発され、独自の製法が確立していった様です。
お酒にまつわる話ですが、私たちのよく使う「くだらない」という言葉の語源としてお酒のことがよく使われます。江戸時代、伊丹や灘など上方から樽に詰められた酒は二十日ぐらいかかって江戸に運ばれました。これを「下り酒」と言います。吉野杉の樽の香が熟成し、江戸の濃厚な料理によく合いました。江戸では酒は下らないとだめで、「くだらない話」の語源になったそうです。また上方の人は新酒を口にすることができたため、料理も薄口、淡泊になった一因であるとの説もあります。
蛇足ですが、「おおばんぶるまい」の語源についてですが、漢字の「大盤」は当て字で、本来は「椀飯ぶるまい」と書くそうです。「椀飯」とは椀に盛った飯のことで、「わんばん」から「わうばん」、さらに「おうばん」へ変化しました。平安時代、公事や儀式のときにお椀に盛った食事が振る舞われることを「椀飯振る舞い」と言いましたが、江戸時代に入ると庶民にも伝わり、正月などに大勢の人を集めて開く酒宴を「大盤振る舞い」と言うようになったそうです。
楽しいお酒の話をさせて頂き会長挨拶とします。
Last Update:2016年04月13日