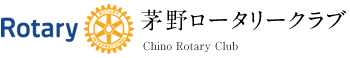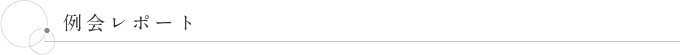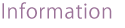4月14日及び4月15日、熊本県において最大震度7という大地震が2度も発生致しました。熊本城も見るも無惨な姿となりました。亡くなられた方々のご家族に対し、心より哀悼の意を表したいと思います。
私たちは日常においても災害の可能性を認識せざるを得ません。皆さんは「特別警報」という言葉をご存知ですか。気象庁は大雨や強風などの気象現象によって災害の恐れがある時にまず「注意報」を、そして重大な災害が起こる恐れのある時に「警報」を出します。大雨については注意報が1時間に25mm以上、警報は1時間で40mm以上です。又、洪水については、注意報が24時間で70mm以上、警報が24時間で110mm以上となっております。気象庁はこれに加え、この警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合に「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。特別警報が出される可能性のある場合については、①18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、②我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」の高潮、③紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者を出した「平成23年台風第12号」の豪雨等が該当します。
「特別警報」は、気象庁が発表する「最後通告のような情報」です。重大な災害が差し迫っているか、重大な災害が進行中の状況で発表されますから、「命を守る行動を」がキーワードになります。
つまり、すでに浸水が発生しているなど、避難が間に合わない状況になっている可能性もあり、その場合、崖の近くなら、崖から離れた部屋などに避難することが必要という意味です。また、まだ避難ができる状況であれば、浸水などが発生する前になるべく早めに避難を行うことが必要です。
特別警報には、大雨のほかに、暴風、高波や高潮、地震、津波、火山の噴火がありますが、さまざまに細分化された情報が増えております。「特別警報」は気象庁が発表する情報の中で最も危険度の高いものですから、発表された際には早急な対応をとらなければなりません。また、「特別警報」は都府県程度の広さで危険な状況にならないと発表されないものですから、特別でない警報や土砂災害警戒警報、河川の洪水警報などが出された時にも、やはり早めの対応が必要だそうです。以上、災害についての豆知識として是非覚えておいて下さい。
以上で会長の挨拶と致します。
Last Update:2016年04月27日