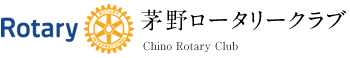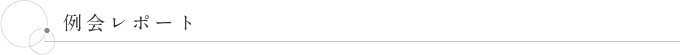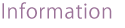本日は、前回の会長挨拶に引き続き防災の話をさせて頂きたいと思います。熊本での大地震に関しましては、5月6日に東海高校に出向き、例会時に募金して頂きましたお見舞金を田中校長先生に差し上げてまいりました。大変感謝して頂きました。
さて、熊本地震につきましては、改めてその恐ろしさを実感した所であります。各市町村におきましては、地域ごとに揺れの強さを示した「揺れやすさマップ」と建物が地震により倒壊する割合を示した「地域危険度マップ」があります。是非この機会に自分の住んでいる地域について、再認識をして頂きたいと思います。
皆さんご存知の事と思いますが、地震には海洋側のプレートの滑り込みの反動によって発生する海溝型地震と、陸地の地殻における活断層のズレによって発生する活断層型地震があります。私たち日本人は、この5年間にこの2つの類型の大きな地震を体験致しました。
それでは地震の大きさについて再確認したいと思います。マグニチュードとは地震の規模を示す単位です。関東大震災はM7.9、阪神淡路大震災はM7.3、東日本大震災はM9.0、熊本大地震はM7.1でした。Mが0.2大きくなると地震のエネルギーの規模は約2倍に、またMが1大きくなると規模は約32倍になります。これに対して震度とは、各場所の揺れの大きさを示します。その地点が実際どう揺れるのかは地震のエネルギー規模だけではなく、震源からその地点までの距離、地盤等の条件に左右されるそうです。それではマグニチュードと震度との関係についてですが、電球の明るさと机の上の明るさとの関係に例えられます。同じ電球からの光でも、机がどの位置にあるかで机の上の明るさは変わります。したがって、マグニチュードが同じ地震であっても、震源が遠ければ震度は小さく、震源が近ければ震度は大きくなります。
幸い私たちの住む諏訪地域は、海から遠く立地するので、津波を伴う海溝型地震の影響は小さいと思われますが、活断層型地震の可能性は十分あります。
諏訪エリアは、諏訪湖を横断する活断層の大熊断層、その北側には諏訪断層群が存し、又、大熊断層の南側には諏訪湖南岸断層群が位置しております。大変恐ろしい話ですが、糸魚川静岡構造線(フォッサマグナ)における地震については、推定マグニチュード8程度で、今後30年以内の地震発生率は14%、東海地震においては、場所は静岡県沖で推定マグニチュード8程度で、今後30年以内の地震発生率は87%となっております。原発の問題も併せて心配となります。災害については対岸の火ではなく、自分のこととして防災意識と防災準備を怠らない様肝に銘じたいと思います。
Last Update:2016年05月11日