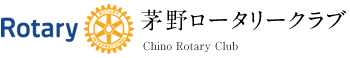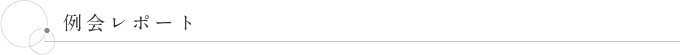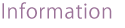みなさんこんにちは
本日は、ガバナー訪問例会ということで、原ガバナーようこそ茅野においで下さいました。後でゆっくりお話をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願い致します。
さて、今日の話ですが、福沢諭吉の話をしたいと思います。
福沢諭吉といえば、皆さん大好きな1万円の顔でありますし、慶応大学の創設者であり、知らない人はいないわけですが、今日は、ちょっと違った面から話をさせて頂きたいと思います。
明治維新によって出現した新政府は、もともとは「攘夷派」の志士たちでつくられました。ところが、新政府をつくった後に彼らが行った政策は、まさに開国です。つまり、日本の国際化でした。これは、攘夷一辺倒で生きてきた連中から言わせれば、大きな裏切りです。そして、この攘夷から開国に踏み切らせるきっかけになったのは、福沢諭吉の『西洋事情』という一冊の本であったと言われています。
明治維新前の幕末に、諭吉は3回外国に行っています。最初はアメリカで、2回目は、フランス、オランダなどのヨーロッパで、3回目は再びアメリカにわたっています。そして、大量の本を買い込んできています。
『西洋事情』を出版したのは、慶応2年のことです。明治維新寸前であります。これは、幕府にとっても、大名にとっても、相当な影響を与えました。はじめて外国の事情が、この本によって具体的に明らかにされたからです。
そのために、「攘夷などというのは空理空論で、とうてい実現できない。小さな島国である日本が、いくら突っ張っても、とうてい外国にはかなわない。攘夷などという空理空論をふりまわすよりも、むしろ国を開いて日本を国際化し、近代社会の一員として国力を増強することの方が大事だ」という考えが、どんどん発展していきました。
その意味では、福沢諭吉が行ったことは、日本の近代化のために、単に外国事情を紹介したにとどまらず、日本の政府の政策を大きく転換させたといっていいと思います。そして、諭吉のやったことで、最も日本の近代化に役立ったのは、「日本をオランダ語社会から英語社会に転換させた」ということです。
福沢諭吉がオランダ語を捨てて英語に走ったのは、彼の痛い経験に基づいています。それまでの日本は鎖国下にありましたが、全面的に外国との交流を断っていたわけではありません。長崎を窓口にして、オランダと中国とは交流していました。オランダは世界各国の中で、日本と交流し続けた唯一の国であり、日本人はオランダ語以外、外国語を知りませんでした。徳川時代に外国の学問を勉強するということは、そのままオランダの学問を勉強するということでした。
福沢諭吉は若いころ、大阪の緒方洪庵の適塾で学びましたが、もちろんここで教えるのも、オランダの学問でした。ここでオランダ語を学んだ諭吉は、あるとき思い立って開国後の横浜に行ってみました。「いままで学んだオランダ語を、実地に試してやろう」と思ったのです。
ところが横浜に行って驚きました。オランダ語など一つもありません。書かれている言葉は、通りの名前を示す表示板も、また各外国の商店に掲げられている字も、すべて英語でした。そして、残念ながら諭吉は、その英語がひとつも読めませんでした。また、会話に使ったオランダ語も、チンプンカンプンでまったく役に立ちませんでした。この日諭吉は深い絶望感に陥りました。今日までの勉学が全部ムダになったからであります。家に戻ったが一晩中眠れず「一体いままで何を学んできたのだ」と口惜しがりました。
オランダ語だ、オランダ学だ、といって、オランダの学問だけを国際社会に進む唯一のものに考えて積み重ねた努力が、まるっきりバカのように思えました。
彼はこの日決断しました。それは、「今まで習ったオランダ語を惜しいが全部捨てよう。そして、あらためて英語を学ぼう」ということであります。福沢諭吉のこの決断の時が、その後の日本の運命を大きく変えたのであります。
福沢諭吉が書いた「西洋事情」や「学問のすすめ」をはじめとして、彼が出版に最も力を入れたのは「英語」の日本導入でありました。これが日本の近代産業発展に大きな役割を果たしたことは、言うまでもありません。
今まで自分が培ってきたものや既得権益が、時代の流れに合わなくなったとき、それを思い切りよく捨てられるかどうか。変革期における発展の分岐点がここにあるのだと思います。
ロータリーは今、会員数の減少や会員の平均年齢の高齢化といった大変大きな問題に直面しており、まさに変革期にあります。そんな中、今年、国際ロータリーは歴史的な決断をいたしました。先週の第一回例会でお話しましたが、規定審議会において、国際ロータリーの定款の規定が改定され、例会は月少なくとも2回開けばよいこととなりましたし、また会員資格についても、会員資格6項目が削除され、会社役員や専門資格者でなくても、主婦でも普通のサラリーマンでも、奉仕する意欲のある人でしたら入会できることになりました。すべてクラブの裁量に委ねられることとなりました。
111年の歴史を持つロータリーが、頑なに守り続けてきた、例会回数や会員資格といったロータリーの金科玉条とも言うべき根幹の規定を切り捨てたという、この決断が、これからのロータリーの発展の転換点になるのではないかと期待しております。
Last Update:2016年09月14日